この記事は、高校野球をこれからする人、もしくはしていた人は、【漫画】名門!第三野球部を読んだ方がいいということをまとめました。
結論から申し上げますと、絶対に読んでおいた方がいいです。読んでおいて損はないです。
私も高校野球をしている時に読みましたが、とても励みになりました。サクセスストーリーです。
それではネタバレ注意で紹介していきます。
あらすじ【ネタバレ注意】
いわゆる推薦入学ではなく、一般入学していて、何の期待もされていない人たちが、ゆるく三軍で活動していたのですが、突然三軍の廃部を通達されたことをきっかけに、這い上がっていく様子が描かれています。
高校野球の名門校で戦力外として扱われていたメンバーたちが、主力選手たちへの下剋上を目指して一致団結し、やがて甲子園制覇という悲願に突き進んでいく姿を描いたスポ根野球漫画。※マンガペディア引用
要するに、【下克上】物語です。笑
 名門!第三野球部(1)【電子書籍】[ むつ利之 ]
名門!第三野球部(1)【電子書籍】[ むつ利之 ]
共感できる点
三軍から這い上がっていくサクセスストーリーを見ることができる
現代では一般入部からのスタートに近い感覚だと思います。
三軍なので、一生懸命に練習をしても日の目を浴びることはないです。
上達したかどうかも、確認してくれる人もいません。
そんな状態なので、サボり倒している人もいれば、一生懸命にまじめに練習する人もいます。
主人公の、檜あすなろは常に一生懸命練習をしていました。その時点で主人公感がでていますね。笑
最終的にはエースとなり、甲子園にも出場し、死闘を繰り広げる姿はまさに下克上であり、究極のサクセスストーリーです。
弱者の戦法が理にかなっている
一軍のスター選手である、海堂タケシ選手は、勝利至上主義の監督に嫌気がさし、監督を殴ったことにより、三軍行きとなります。
三軍行きとなったことで、野球部を退部しているような、退部寸前の状態となっていました。
今回、三軍を廃止するとのことで、なんとか野球を続けたい主人公の檜あすなろが何度もお願いをして、三軍に加わってもらうこととなりました。
海堂タケシ選手が兼任監督として三軍入りする点が、ターニングポイントとなりました。
三軍存続条件として、一軍との最後の試合に勝つことであり、その奇跡を信じて猛特訓がはじまりました。
ここから弱者の戦法が始まったのです。
投手はコントロールが一番大切
海堂タケシは、投手の檜あすなろに対して、徹底的に四隅のコントロールを磨かせます。
まさにこの事が弱者が強者に勝つ合理的な戦法だと思います。
野球をしていた人ならわかると思いますが、どんな球威であってもアウトローのボールは打ちにくいですよね。
四隅になげきるには、理にかなった投げ方で投げないと、ボールが垂れてしまうので難しいです。
非常に理に適った練習といえます。
石ころがたくさんある河原での守備練習
石ころがたくさんある河原でノックは絶対に受けたくありません。怪我をします。普通なら病院送りです。
公式ボールが不規則に変化し続けるので、恐怖でしかありません。
しかし、その恐怖心を克服すれば、超効率的な守備練習となるでしょう。
漫画の描写では、顔面がボコボコになりながら、日々河原ノックで上達する様子はシュールそのものでした笑
ある意味、最短で守備を上達させる理にかなった練習なのかもしれません笑
野球はバッテリーが大切だと改めてわかる
最終的には、一軍の試合に勝つことになるのですが、その試合の立役者は、やはり投手の檜あすなろと、捕手の海堂タケシです。
つまり、漫画であっても実際のプレーであっても、結局はバッテリーの能力が高くないと勝利できないということがわかります。
1人は抜きん出た選手がいないと勝つことはできない
海堂タケシ選手は元々一軍の顔の選手です。
結局その選手がホームランを打ち、勝っているので、軸となる選手はもともと三軍の選手にはいなかったということです。
現実世界でも、初めから三軍というより、一般入試で入部した人は、自分自身の特徴を理解してプレーをすることで、試合に出場できるチャンスが増えるのかもしれないですね。
面白い点
二軍の選手がほぼ出てこない
二軍の選手は、玉拾いの描写で初めにちょろっとしかでてきていません。
二軍は実はないのではないか説があります。笑
元一軍のエースが三軍出身
元一軍のエースである投手が、実は三軍出身でしたが、その描写が少なめです笑
その点を踏まえても、二軍は存在しない説が有力です。w
監督も最終的に戻ってきて、監督の娘と三軍の選手が結ばれる
海堂タケシ選手の話です。
闘病を支えていた女性が、実は殴った監督の娘であり、監督が勝利至上主義なのは体が弱い娘のためでもあり、海堂選手はその監督の娘と結ばれます。
深夜ドラマでもびっくりの展開がありました。
這い上がっていく姿は野球部にとって大事な考えなので共感できました!
全体を通して、這い上がっていく姿は野球をしている、もしくはしていた方からすると、非常に共感をえられるのではないかと思います。
皆さまも一度読まれてはいかがでしょうか。
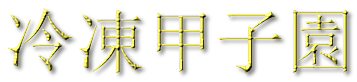



コメント