この記事は野球の流れとは何か、またどのような状況で流れが変わってしまうかを説明します。
野球を経験したことのある人ならば、必ず耳にした事があるかと思います。
「今のプレーで流れを呼び込んだよ」
「ちょっと流れが悪くなりそうだな」
様々な人が流れという言葉を平然と使いますが、あまり違和感はありませんよね。
そもそも流れとは一体なんでしょうか。
説明をしていきます。
野球の流れとは?
野球の流れとは、ターニングポイントとなった場面、分岐点を指す事が多いです。
流れを呼び込んだプレーであったり、この失敗で流れを相手に渡してしまったなど、プレー後に流れという表現を使うことか多いです。
具体的にどのようなケースで用いられるのかを解説していきます。
流れの具体的なケース
流れの具体的なケースですが、たくさんのケースがある中で、今回は3つのケースを想定しました。
チャンスで凡退した
「5-4で勝っている状況で、ノーアウト満塁のチャンスを作り、追加点が取れる状況で、追加点が取れなかったので、流れが相手チームに行きそうだ、嫌な流れだな」
チャンスで点が取れないと、流れが相手チームに行ってしまうと思う人は多いです。
ピンチの後にチャンスありという格言がありますが、その典型例でしょう。
確かにチャンスを作って点が取れないと、気落ちしてしまいます。
気落ちする=流れを渡すという心理となっているのかもしれません。
ピンチで抑えた
チャンスで打てなかったの守備側で、ピンチを抑えたとなると、チームは盛り上がり、逆転の機運が高まります。
「ピンチを凌いだので、流れがくるぞ」もしくは、
「ピンチを凌いだということは、まだ流れがこっちにあるぞ」
と2パターンの流れの使い方があります。
流れという表現は都合がいいのかもしれません。
投手を交代した
点差を追い詰めて、先発投手を降板させて、次の投手が出てきた際などに、
「先発投手を引き摺り下ろしたぞ、流れかこっちに来ている」や、
「ピッチャーが変わったぞ、流れが変わるぞ」などと、投手交代を変化と捉えて、流れが変わるという人は多くいます。
継投で打たれるインパクトが大きいからでしょうか。そのようにいう人は多いのです。

流れというのはデータではないと証明されている
大学の教授が、野球には流れが実際にあるのかといった研究をして、実際には流れなどないということかわかりました。

それはその通りではあると思います。
なぜなら、いくら流れがあろうとなかろうと、好投手には流れなど存在しないケースがほとんどだからです。
打てないものは打てないです。つまり、絶対に叶わない相手には、流れなど意識する状況にもならないということでしょう。
経験の刷り込みで流れがあると思ってしまう、心理的に流れが発生している
流れがデータ上はないとはいえ、競った展開ですと、流れを意識することは多いでしょう。
流れを呼び込むような、ルーティンなどもあります。
験担ぎをすることもその1つ
例えば試合前にカツ丼ばかり食べたり、靴紐を必ず右足から縛るなど、ルーティンの行動、現被衣も流れ、勝利を呼び込む行動の1つでしょう。
人は違和感を嫌いますので、いつもと同じことをして、流れを呼び込んでいくことを大切にしたいのでしょう。
重圧を与え続けることもその1つ
相手に重圧を与えるという表現も抽象的ですが、それも流れを渡さないということの1つでしょう。
重圧を与え続けるケースは、負けている状況で、いつ逆転してもおかしくないような状況を毎回作ることです。
その状況を作ることで、負けているのに有利に試合を展開しているような状況を作る事ができます。
その現象も、流れの1つと言えるでしょう。
まとめ
流れはデータとしては存在しないとはいえ、野球には流れという言葉が必ず付き纏います。
流れとは、エラーをしないなどの凡事徹底により、離れないものだと思いますので、凡事徹底をしていきましょう。
こちらの記事もおすすめです。

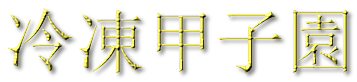

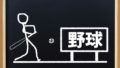

コメント