この記事は高校野球において練習中に音楽を流さないで練習をしている高校がほとんどですが、なぜプロ野球チームが取り入れているのにもかかわらず、高校野球では取り入れられないことを、検証しました。
なぜ音楽を聴きながら練習をすることができないのか
音楽を聴きながら練習をすることは、緊張感も取り除くことができ、良い雰囲気で練習をできると想定できます。
しかし昔ながらの指導者は、そのようなことを容認することはほとんどありません。
高圧的に指導をし、指導者自身の管理下に置いておきたいからです。
そのため、音楽を流しながら練習をすることはほぼ無いのです。

練習は緊張感をもって行うべきという間違い
「試合では緊張感があるので練習でも緊張感を持って取り組むべきだ」
そういった考えのもとで、緊張感を持って練習をする指導者が大勢おります。
しかし、ほど良い緊張感は大切かもしれませんが、常に緊張しているような状態では委縮をし、逆効果ではないでしょうか。
野球の練習以外の無駄な部分ばかりに力を入れてしまうので、音楽を聴きながら練習をする以前の問題となっています。
声を大きく出すことの無意味さの強要により音楽は邪魔
今現在も、グラウンドで大声を出す人が正しいといった風潮があります。
実力があっても、声の大きさが小さいだけで試合に出場できない人も中にはいるでしょう。
高校野球にはそのような謎の文化が存在しております。
ですので音楽を聴きながら練習をしてしまうと、声出しがしにくいような状態となりますので、その面でも音楽を聴きながら練習をすることができないと想定できます。
声出しが必要ではないことをまとめた記事はこちらです。

指導者が絶対であり他の意見が取り入れられることは少ない
どこの野球部もそうですが、指導者が全ての練習や試合などのスケジュールを決めています。
それが当たり前のように感じますが、裏を返せば選手には一切主体性がありません。
限られた範囲の中、例えば指導者不在の自主練習のみくらいでしか自分で物事を決めることがなくなります。
上の人に従順な人が完成されていくのです。
 【ふるさと納税】野球ボール 送料無料 (公財)全日本軟式野球連盟公認球 ケンコーボールJ号(5ダース)N09006
【ふるさと納税】野球ボール 送料無料 (公財)全日本軟式野球連盟公認球 ケンコーボールJ号(5ダース)N09006
以前に比べれば柔軟だが音楽を取り入れている学校はほぼない
近年、徐々に坊主の強制化をやめたり、また週に1回休みを設けたりと、依然の高校野球の部活動に比べると柔軟になってきた印象です。
しかし練習風景自体は、未だにはつらつ、キビキビしとしたような光景が多いので、リラックスして楽しく練習をするような文化はありません。
軍隊のような練習がいまだに美化されている面がある
軍隊みたいな練習が未だに美化されていることが問題です。
例えば全員で列になって行うランニングなど、掛け声と、走り方は縦横にリズムを合わせて走ることを行いますが、まさに軍隊そのものです。
それを全員で上達しても、野球など上手くなりませんし、意味のないランニングの強要なので時間の無駄です。
そのような無駄なことが今も強要されているのです。
グラウンドに活気があることが目的となっている
野球を上達することや、野球を楽しむこと、またチームとしては甲子園に出場することが本来の活動目的であるはずです。
しかし、その1日のグラウンドの活気ばかりを求められ、ただ大声をだして満足しているような人が大勢います。
グラウンドに活気があることが目的となってしまい、本末転倒の状態となっているのです。
まとめ
柔軟な考えのできない指導者が現在も指導に当たっているケースが多いため、音楽を流しながら練習をするなどの対応をすることができない学校が多いです。
そういった柔軟な考えができない指導者は、引退してもいいのではと思います。
また進路選択でも、柔軟な考えを取り入れる指導者、チームに入団するべきでしょう。
野球をする子供が減っていく中で、柔軟な考えのできるチームが増え、今後はまた人気のスポーツになれることを願っています。
おわり
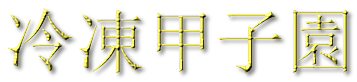



コメント